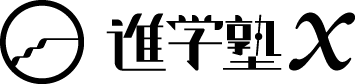どうも塾長です。
最近は、インスタで公私混同甚だしいストーリーを連投しまくっており、ブログはご無沙汰しておりました。
インスタフォロワーの皆様は、塾の様子を知るためにフォローしてくださっているはずなのに、ニーズを考えない投稿、大変失礼しましたm(_ _)m
夏期講習が無事終わり、二学期中間テストもほとんどの中学が終わり、残すは平坂中のみとなりました。
ブログでしっかりとした文章を書く時間と気力が戻ってきましたので、今日からまたぼちぼちと再開していこうと思います。
テスト前日の授業を欠席する子が、今回は多くいました。
これは決してネガティブなことではなく、事前準備が万全である何よりの証拠であり、あとは自分でどれだけ覚えられるか次第だという当事者意識の表れの証拠です。
成績を上げるために必要なことは、シンプルに
●事前準備を万全にすること
●当事者意識を持って取り組むこと
これに尽きます。
ただ
「事前準備を万全にする」
の認識が人によってバラバラなので、蓋を開けてみると
「5教科480でした!」という子もいれば「350しか取れませんでした。。」という子も出てきます。
では「事前準備を万全にする」というのは、どのようであれば良いのか?
それは
「客観的な事実に基づいて、問題ないことの確認が取れている状態」
です。
もう少し噛み砕くと、
「テスト範囲の問題を、直前の段階で、手を動かして解いてみた結果、丸になる状態」
と言えます。
ここには
「上記の状態+瞬殺できる」
「上記の状態ではあるものの、すぐに答えが出てくるものばかりではない」
などグラデーションが存在するので、その中で400であったり、450であったり、470であったりバラつきが発生してきます。
そこは良いとして、問題は「事前準備を万全にした」はずなのに350くらい(もしく70を下回る教科がある)になってしまう子です。
(「事前準備が万全ではない」のはそもそも論外なので、勉強法云々の前に、しっかり時間を確保してください。そして脳死状態で良いので範囲に書かれている問題を全て3回はやりましょう。いやでも300は超えます。)
「万全」の基準が激甘です。
「完璧です」「大丈夫です」「できます」
の基準が、ほとんど主観による判断である場合が多いです。
実際に手を動かしてないのに、さらっと読んだだけで、「できる判定」を下してしまっています。
つまり「多分できるだろう」と「できます」を混同しています。
「頭の中でなんとなく理解した状態」と「実際に手を動かして解ける状態」には雲泥の差があります。
とかくアウトプットは手を動かすべし。
「できる」は実際に解いて判定すべし。
と心得てください。
真にできる子は、良い意味で「臆病」なんです。
「本当に本番できるか?」
常に意識がそこに向いています。
あらゆる手段を使ってそこの確認に尽力します。
「コレに似たような問題をください」→聞かれ方が変わってもできるか?
「歴史の第二次世界大戦後からの流れが不安なんで、確認してください」→単語を覚えただけになっていないか?
など余念がありません。
テストが返ってきて、自分の想定より低かった場合、
「事前準備は本当に万全だったのか?」
に目を向けてください。
そしてそれを今後の学習姿勢に活かしましょう。
常に改善する姿勢があれば、成績はどんどん上がっていきます。
今回ダメだったから、これからもダメだ。
ではなく、
今回ダメだった。次はどうしたらもっと良くなるだろう?
この姿勢でいきましょう!
それでは。